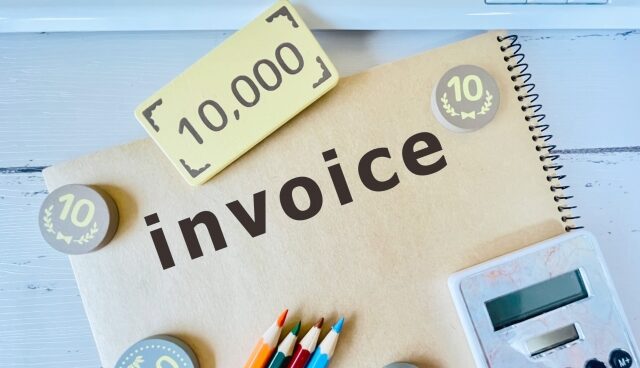
インボイス請求書例【建設業向け】:新制度への対応と書き方のポイント
公開日:2025.02.21
▼ 目次
2023年10月から導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、建設業界でも無視できない大きなトピックとなっています。請求書を作成する際には、これまでの書式に加えて「登録番号」や「税率ごとの消費税額」などの必須項目を正確に記載しなければ、仕入税額控除が認められなくなる可能性があります。
本記事では、インボイス請求書例に合わせた書き方や新制度の注意点、また建設業ならではの対応ポイントをわかりやすく解説します。業務効率と法令遵守を両立させるためのヒントとして、ぜひ参考にしてください。
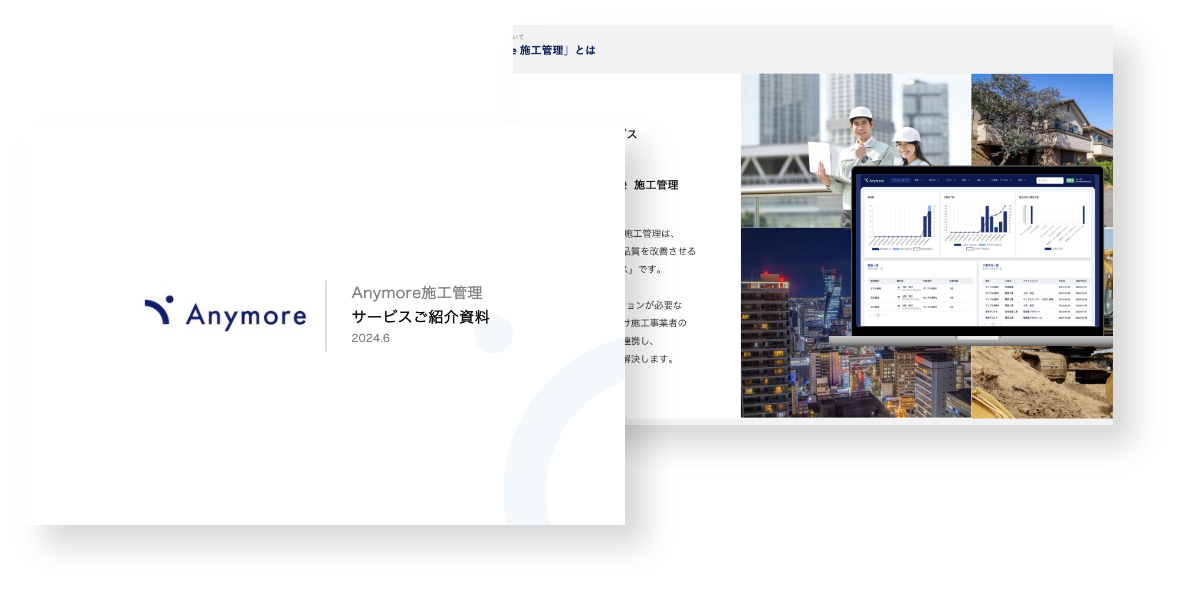
サービス資料ダウンロード
見積作成や請求処理などの受発注業務をそろそろエクセルから卒業してDXを実現したい担当者様向けに業務効率化につながるAnymore施工管理の概要について紹介しています。
参考記事(外部サイト):インボイス制度で変わる建設業界!3つの注意点と準備をわかりやすく解説
参考記事:建設業の請求書の書き方を解説!人工費の計算方法やインボイス制度の対応も!
1. インボイス制度とは
1-1. 制度の概要
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除を受けるために、適格請求書発行事業者(通称インボイス事業者)が発行する請求書を保存する必要がある仕組みです。請求書には、これまで以上に正確な消費税額や取引内容を記載することが求められます。
1-2. 建設業への影響
- 材料費や下請業者との取引が多い建設業では、インボイス制度に対応していないと、仕入税額控除を十分に受けられなくなるリスクが大きいです。
- 請負工事では、元請けや下請け間の請求書発行が複雑化しやすいため、正確なインボイスの発行・保存が不可欠となります。
2. インボイス請求書に必要な項目【建設業向け】
インボイス請求書は、従来の請求書よりも記載事項が増えています。主な必須項目は以下のとおりです。
- 適格請求書発行事業者の登録番号
税務署に登録した際に付与される番号を記載。 - 取引年月日
請求書を発行した日付、および取引の実施日や工事完了日など。 - 取引内容の明細
工事の名称、材料の品目、数量、単価など具体的に記載。 - 税率ごとの消費税額・税率区分
標準税率(10%)と軽減税率(8%)が混在する場合、それぞれの合計額と消費税額を区別して記載。建設業ではほとんどの場合10%だが、飲食施設を含む工事などでは注意が必要。 - 請求金額の合計(消費税額を含む)
工事全体の合計金額を明記。 - 請求書発行者の名称・住所・連絡先
会社名、所在地、電話番号など。社判を押す場合は、社名が重複しないように配置。
これらの項目を漏れなく、かつわかりやすく記載することが、インボイス請求書作成の基本です。
3. インボイス請求書例【建設業向け】
以下は、実際の建設業務を想定した簡易的な請求書例です(あくまでもサンプル)。実運用では各社の書式や追加項目(工事着手日・完了日、支払条件など)に合わせて調整してください。
---------------------------------------------------------------------
インボイス請求書 (適格請求書)
---------------------------------------------------------------------
【 請求書番号 】 2023-ABC-1001
【 発行年月日 】 2023年10月10日
【 登録番号 】 T1234567890123
【 請求先 】
株式会社○○○○
〒123-4567 東京都千代田区XXXXXX
担当:△△ △△ 様
【 請求元 】
株式会社□□建設
〒987-6543 東京都中央区YYYYYY
登録番号:T1234567890123
TEL:03-XXXX-XXXX / FAX:03-XXXX-XXXX
担当:□□ □□
【 工事名 】 ○○ビル 外装改修工事
【 工事期間 】 2023年9月1日 ~ 2023年9月30日
---------------------------------------------------------------------
内 訳 数量 単価 金額 税率
---------------------------------------------------------------------
1) 足場組立費 300㎡ 1,000円 300,000円 10%
2) 外壁塗装費 一式 --- 600,000円 10%
3) 養生・清掃 一式 --- 100,000円 10%
小 計 1,000,000円
消費税(10%) 100,000円
---------------------------------------------------------------------
請求金額合計 1,100,000円
---------------------------------------------------------------------
※お支払いは○○銀行××支店 普通口座 0123456 (株)□□建設 へ
2023年10月末までにお願いいたします。
---------------------------------------------------------------------
ポイント
- **「適格請求書発行事業者の登録番号」**を記載。
- 税率ごとに合計額と消費税額を分ける。今回はすべて10%として統一。
- 数量や単価を明確に。外注費や資材費が混在する場合、より細かく明細を分けるとトラブル防止につながる。
4. 新制度への対応:建設業の注意点
4-1. 元請と下請の関係
請負建設業では、元請が下請に支払う工事費にもインボイス制度が適用されます。下請業者がインボイス発行事業者でないと、元請側が仕入税額控除を受けにくくなるため、取引業者を選定する際には登録の有無を確認しましょう。
4-2. 軽減税率との混在
基本的には工事に軽減税率は適用されませんが、食堂設備の新築工事や飲食関連施設の改装など、一部8%が含まれる場合があります。その場合は、税率区分を分けて請求額を記載します。
4-3. 消費税額の計算ルール
インボイス制度では1円未満の端数処理がより厳密に問われるケースもあるため、税計算の方法を社内で統一し、税別合計×税率でしっかり計算するようにしましょう。
5. インボイス導入後の運用ポイント
5-1. 請求書の電子化
紙の請求書を郵送する方法に加え、電子請求書(PDFなど)をメールやクラウド経由でやり取りする企業が増えています。インボイス制度に対応したフォーマットであれば、電子保存でも仕入税額控除が認められるので、経理効率の向上につなげることができます。
5-2. 請求書管理システムの導入
建設業では一件ごとの金額が大きく、取引先も多岐にわたるため、手作業だとミスや抜け漏れが起きやすいです。請求書管理システムや会計ソフトを活用し、登録番号の自動チェックや消費税区分の仕分けをシステム化することで、トラブルや業務負荷を軽減できます。
5-3. 社内研修とマニュアル整備
現場担当者や経理スタッフがインボイス制度を理解していないと、書類不備で仕入税額控除を受けられない恐れがあります。
- 全社員向けの勉強会やマニュアル作成
- 定期的な法改正情報の共有
これらを通じて、社内で一定のルールとフォーマットを持って運用することが大切です。
6. まとめ
インボイス請求書 例 建設業を意識した書類作成は、請負建設業においても避けて通れない課題です。新制度に対応しないまま従来の書式で請求書を発行していると、仕入税額控除が受けられなくなるなど、経理面で大きな損失が出る可能性もあります。
- インボイス制度では、登録番号や税率ごとの消費税額などの記載が必須
- 建設業の請求書には、工事内容や人件費、材料費など細かく明示すると、トラブル防止に効果的
- 元請・下請間での取引も、インボイス発行事業者かどうかを相互に確認しておく
- 電子請求書やシステム導入により、業務効率と法令遵守を両立可能
今後もインボイス制度は運用上のガイドラインが更新される可能性がありますので、最新の情報を常に確認しながら、建設業界の特性に合った書式・運用体制を整えていきましょう。



