
工事写真の撮り方:黒板の書き方や撮影ポイントを徹底解説
公開日:2025.02.21
▼ 目次
建設現場やリフォーム現場では、施工の進捗や品質を記録するために「工事写真」が欠かせません。なぜなら、工事写真は後々のトラブルや追加工事の際に重要な資料となり、発注者への報告や行政手続きにも利用されるからです。しかし、工事写真の撮り方には独自のルールやマナーがあり、慣れていない人にとっては「どのように撮ればいいのか分からない」と感じる場面も多いでしょう。
本記事では、工事 写真 の 撮り 方の基本から、工事 写真 黒板 書き方とその配置方法、さらに現場 写真 撮り 方のポイントまで、徹底的に解説します。正しく写真を撮ることは現場管理の効率化にもつながるため、ぜひ参考にしてみてください。
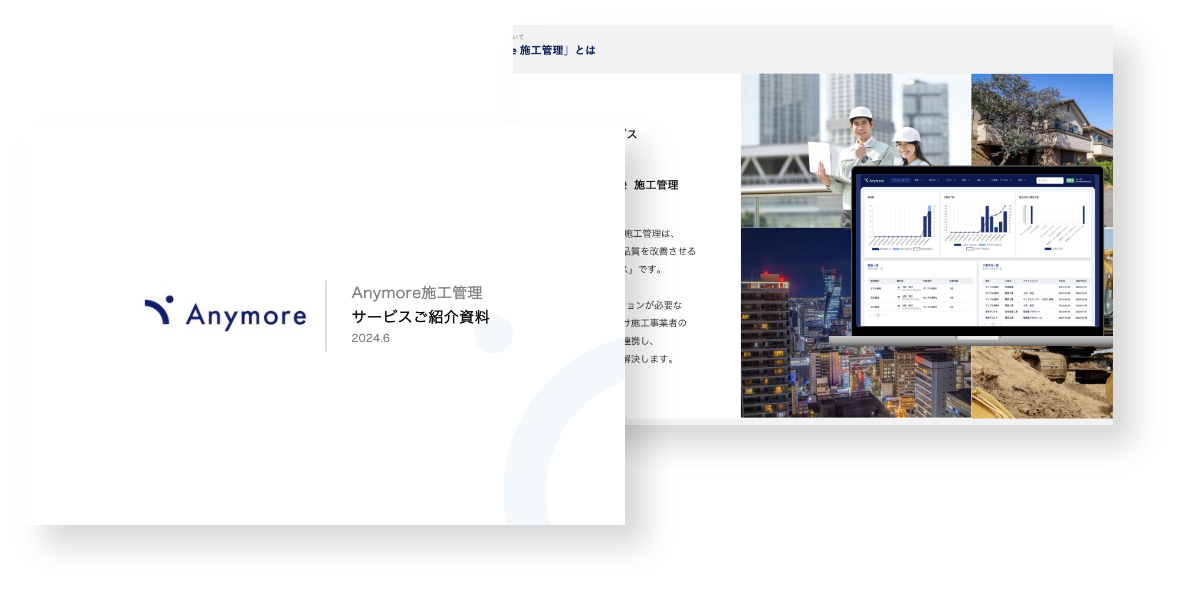
サービス資料ダウンロード
撮影した工事写真の管理ならAnymore施工管理がおすすめ!写真管理・写真台帳作成業務を劇的に効率化できる施工管理アプリ「Anymore施工管理」の概要について紹介しています。
参考記事:工事写真の撮影・管理での注意点とは?工事写真に必要なポイントを解説!
参考記事(外部サイト):工事写真の撮り方の4つのポイント|効率的な管理方法も
工事写真が重要な理由
書類・報告のエビデンスとして
工事写真は、施工完了後に作成する書類や報告書に添付されることが一般的です。以下のようなケースで強い効力を発揮します。
- 発注者への報告資料
- 役所や監督機関への提出資料
- 保証や保険申請のためのエビデンス
- 施工不良やクレーム発生時の原因究明
もし適切に撮影されていないと、**「いつ」「どこで」「どのように」**工事が行われたのか判断しにくくなり、後のトラブルに発展する可能性があります。
追加工事・変更工事への対応
工事途中に仕様変更や追加工事が発生した場合にも、写真があればどこからどこまで施工が進んでいたかが明確に分かります。記録が曖昧だと、追加費用の正当性をめぐって紛争が起きる可能性もあるため、正確な工事写真があることは双方にとってメリットとなります。
安全・品質管理
建設現場は常に変化しており、足場や配筋の状況などは日を追うごとに変わっていきます。写真をこまめに撮影・保管しておけば、安全対策や品質不良の早期発見にも役立ちます。たとえば、コンクリート打設前の配筋写真から不適切な施工を発見できる場合もあります。
工事写真の基本的な撮り方
1. 撮影前の準備
- カメラのチェック
電池残量やメモリの容量を確認し、予備のバッテリーやメモリカードを準備します。 - 撮影日時の設定
カメラやスマートフォンの日時設定を正しく行い、写真データのタイムスタンプを正確にします。 - 現場の清掃
不要な機材やゴミが写り込まないように、必要最低限のものだけを残すのが理想。写真の見やすさが大幅に変わります。
2. 撮影時の姿勢とアングル
- 水平・垂直を意識する
余計な傾きがあると、後で写真を見た際に位置関係が分かりづらくなります。 - 全体と部分を撮る
建物や施工箇所の“全体像”と、施工細部の“拡大図”の両方を撮影しましょう。図面や仕様書と比較する際に分かりやすくなります。 - 自然光を有効活用
屋外工事の場合は、太陽光を背にして撮影するのが基本です。逆光を避け、影が落ちないように注意します。 - 重要な寸法はメジャーを写す
配管や設置位置の寸法を記録する場合、メジャーを併せて写すことでサイズを客観的に確認できます。
3. 撮影タイミング
- 工程の節目ごと
基礎配筋、コンクリート打設、内装仕上げなど、工程が切り替わるタイミングで撮るのが鉄則です。 - 変更箇所やトラブル発生時
設計変更や突発的な問題が発生した際にも、原因と対応策の記録として写真が有効です。 - 施主や検査員が立ち会う前後
施主検査や行政検査の前後で写真を撮っておくと、後日の確認や議事録代わりになります。
黒板の書き方と配置のコツ
黒板の役割
工事写真では、「どの現場で、どの工程の写真なのか」を明確に示すために黒板(ホワイトボードでも可)を使います。黒板に必要な情報を書き込んで写真に写し込むことで、紙やデータ管理の段階で写真と説明が食い違わないようにするのが目的です。
黒板に書くべき情報
- 工事名
例:「○○ビル新築工事」「△△邸リフォーム工事」 - 施工箇所・工程
例:「基礎配筋」「外壁タイル貼り」「電気配線工事」 - 撮影日時
できれば「○年○月○日 ○時○分」と具体的に。 - 会社名や担当者名(任意)
必要に応じて施工会社名や現場担当者名を入れる場合もあります。
書く文字は大きく、読みやすいように心がけ、略語や専門用語もなるべくわかりやすく表記します。
黒板の配置・撮影テクニック
- 撮影対象物の正面に黒板を置く
対象物と黒板が重ならないよう、かつ黒板の文字がはっきり読める距離を保ちます。 - フレームの3分の1程度に収まるように
写真全体が黒板で埋まらないよう、かつ黒板の文字が読める大きさを意識します。 - 反射や影に注意
屋外で撮影する際、黒板が光を反射して文字が見えにくくならないよう、角度を微調整しましょう。 - ホワイトボードの場合
屋外では文字が反射しやすいため、ボード表面をマット加工にするか、直射日光を避ける工夫が必要です。
現場写真の撮り方のポイント
全景写真と部分写真の組み合わせ
「全景写真」は現場全体の様子や作業範囲を把握するのに役立ちます。一方、「部分写真」は基礎配筋や電気配線、内装仕上げなど、工程の詳細を正確に記録するために重要です。この2種類を組み合わせて撮影し、それぞれに黒板を写すか、もしくは全景には黒板なしで部分写真にのみ黒板を写すなど、写真の使い分けをする方法があります。
施工前・施工中・施工後の3ステップ
たとえば、天井裏の配管や断熱材などは、施工後には目視確認できなくなる部分が多々あります。そのため、「施工前(配管設置前)」「施工中(配管敷設中)」「施工後(天井を塞いだ後)」というように同じ箇所を段階的に撮影するのが理想です。こうすることで、工程ごとの状態を比較・検証でき、万が一の不具合発生時にも対応がスムーズになります。
撮影枚数の目安
工事の規模や工程数によっても異なりますが、多めに撮っておくのが基本です。撮影後に不要な写真を削除するのは簡単ですが、必要な写真が足りないと取り返しがつきません。また、最近はデジタルカメラの容量やクラウドストレージの活用でデータ管理が容易になっているため、過度な枚数制限はせず、工程ごとに十分なカットを残すことを推奨します。
撮影後のデータ管理方法
ファイル名の付け方
撮影後は写真データをパソコンやクラウドに取り込み、わかりやすいファイル名を付けて整理します。たとえば、「工事名_工程名_撮影日_通し番号」などのルールを決めると、後から検索しやすくなります。
例:
コピーする編集するABCビル_基礎配筋_20230315_001.jpg
ABCビル_基礎配筋_20230315_002.jpg
フォルダ構成
プロジェクト別や工事箇所別、工程別など、必要に応じた階層構造を作りましょう。大規模な現場では、さらに日付や担当者別のフォルダを作って分類するなど、チーム全体が同じルールで管理できる状態が理想的です。
クラウドストレージの活用
複数の担当者が同じ写真データを扱う場合、クラウドストレージ(DropboxやGoogle Driveなど)を使って共有するのがおすすめです。
- メリット
- 即時共有が可能
- デバイスを選ばずアクセスできる
- バックアップの安全性向上
- 注意点
- ファイル名やフォルダ構成のルールを統一しておく
- 権限設定を慎重に行い、機密情報が漏れないようにする
トラブルを防ぐための注意点
写真の改ざんや加工
工事写真は重要な「証拠」となるため、意図的な改ざんや不必要な加工は厳禁です。色補正や切り抜きも状況によっては“改ざん”とみなされる可能性があるため、必要最低限の編集にとどめ、原本データを必ず保管しておきましょう。
個人情報やプライバシー
現場周辺の住民や車のナンバープレートなど、プライバシーに関わる情報が写り込んだ場合は、配慮が必要です。工事写真の提出先によっては、不要な背景をマスク処理するなどの対応を行い、トラブルを防ぎます。
定期的なバックアップ
万が一のデータ消失を防ぐため、外付けハードディスクやクラウドストレージへの定期的なバックアップは欠かせません。ハードディスクが故障したり、クラウドのサービスが停止したりするリスクも考慮し、二重または三重のバックアップ体制を整えておくと安心です。
まとめ
建設現場における「工事写真」は、ただ撮ればいいというものではなく、どのように撮るか、何をどのタイミングで撮るかが非常に重要になります。
- 工事 写真 の 撮り 方:水平や光量などの基本を押さえ、全景と部分の両方を撮る
- 工事 写真 黒板 書き方:工事名や工程、撮影日時などを大きくわかりやすく記載し、写真の中で読みやすい位置に配置する
- 現場 写真 撮り 方:工程ごとにタイミングを見極め、施工前・施工中・施工後の3ステップで撮影すると資料性が高まる
正しく撮影された工事写真は、後日の変更工事やクレーム対応、安全管理の証拠、さらには企業の信頼獲得にも大きく貢献してくれます。日々の作業に追われてしまいがちですが、写真撮影の質とルールをしっかり確立しておくことが、効率的でトラブルの少ない現場管理へとつながるのです。ぜひ本記事を参考に、より分かりやすく、正確な工事写真を残していきましょう。


