
工事請負契約書とは?基本構成と作成時の注意点を徹底解説
公開日:2025.02.21
工事を発注・受注する際に、必ずといってよいほど交わされるのが「工事請負契約書」です。これは建設業界に限らず、建築・土木・設備などさまざまな工事における契約の基本となる重要な書類です。しかし、工事請負契約書の詳細や「建築請負契約書」との関係、さらには印紙税の扱いについて正しく理解している人は意外と多くありません。本記事では、工事請負契約書とは何か、どのような構成になっているのか、そして作成時の注意点について詳しく解説します。あわせて「請負契約印紙代」に関する実務面の注意点なども取り上げますので、ぜひ最後までご覧ください。
参考記事:工事請負契約書に必要な印紙税とは?収入印紙の貼付ルールと軽減措置を解説
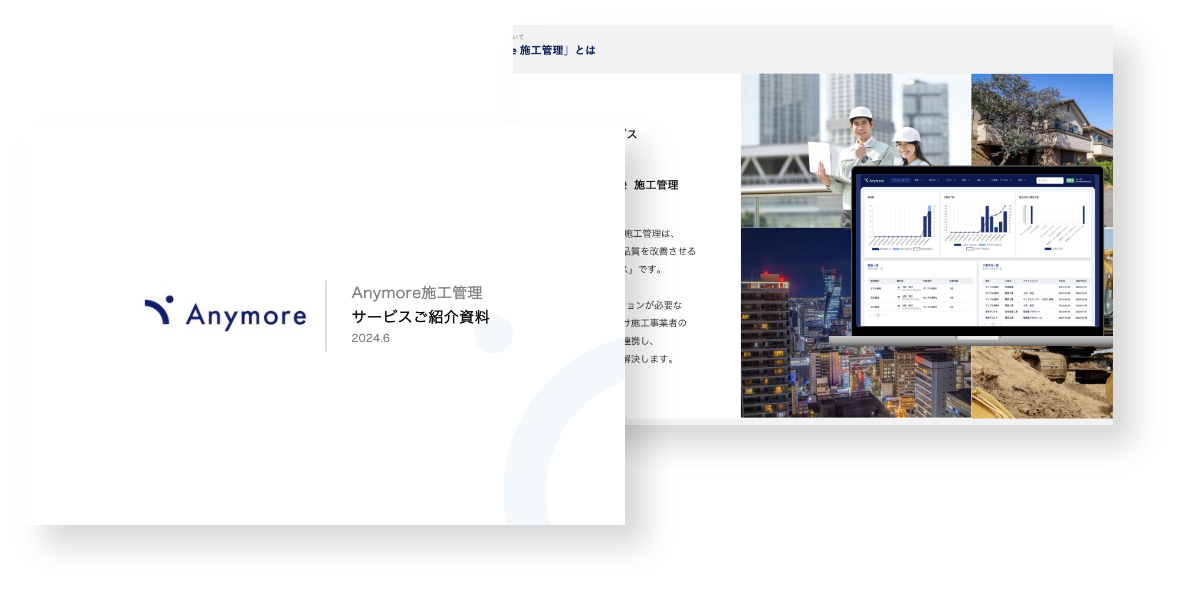
サービス資料ダウンロード
工事請負契約書の管理ならAnymore施工管理!案件に紐づけて契約書を管理できるので誰でもすぐ契約書の内容を確認できます。この資料はAnymore施工管理の概要について紹介しています。
工事請負契約書とは
工事請負契約書とは、工事の完成とその対価の支払いを約束する「請負契約」の内容を文書化したものです。工事の対象や工期、工事金額、支払い条件など、工事を進めるうえでの重要事項を明文化します。文字どおり「請負契約」なので、工事を請け負う側(受注者)が、発注者から提示された仕様や条件に基づいて工事を完成させる義務を負い、発注者は工事の完了に応じて報酬を支払う義務を負うことになります。
工事請負契約書と建築請負契約書の違い
「工事請負契約書」と「建築請負契約書」は、厳密には表現が異なるだけで、法的には同じ意味合いを持つことが多いと考えられます。建築に限定した工事の場合、建築請負契約書と呼ばれるケースが一般的です。しかし土木工事や設備工事なども含む場合は「工事請負契約書」と総称したり、より包括的な呼び方をすることがあります。
- 工事請負契約書:土木、設備、電気など建築以外の工事も含めて広く利用
- 建築請負契約書:建築工事のみを対象とする書式や用語が用いられる傾向
工事の種類や範囲によって使い分けられることがありますが、基本的には「契約書」としておさえるべき項目・ポイントは共通です。
工事請負契約書の基本構成
工事請負契約書には、一般的に以下のような内容が盛り込まれます。これらの項目を網羅していないと、後になって**「聞いていなかった」「合意していなかった」**というトラブルが発生するリスクが高まります。しっかりと把握しておきましょう。
1. 発注者・受注者(請負人)の情報
契約当事者となる発注者(施主、クライアントなど)と受注者(請負人)(工事業者)の氏名・名称、所在地、代表者などを明記します。個人事業主の場合は個人名と住所、法人の場合は法人名や本店所在地などを正確に記載することが重要です。また、連絡先や担当者名も加えておくと、コミュニケーションミスを減らせます。
2. 工事内容と範囲
契約の肝となる工事内容とその範囲を明確にします。建築工事であれば建物の構造や規模、仕上げの仕様などを詳細に記載し、土木工事の場合も施工箇所や仕様書の参照先などを細かく示すことが重要です。また、追加工事や変更工事に対する取り扱いも明確にしておくと、後日追加費用を巡るトラブルを回避しやすくなります。
3. 工期と引き渡し
工事着手日から完了日、引き渡し日など、スケジュールに関する取り決めを行います。天候不順や資材不足などで工期延長が不可避となる場合の扱いをどうするかも盛り込むことが多いです。また、工事完了の判定基準や検査方法(中間検査、完了検査、施主検査など)を定めておくことで、**「いつ工事が完成したとみなすのか」**をめぐる紛争を防ぎます。
4. 契約金額と支払い条件
工事請負契約の要ともいえるのが契約金額と支払い条件です。総額を記載するだけでなく、支払時期や支払方法(分割払い、一括払い、着工金・中間金・完了後残金など)、消費税の取り扱い、遅延損害金の利率などを明記します。
また、追加・変更工事が生じた場合の金額算定方法を規定しておくことも重要です。これが曖昧だと、後から高額な追加費用を請求されたり、逆に受注者側が赤字を被るリスクが高まります。
5. 契約の解除・変更条件
工事中に想定外の事態が発生したり、発注者が資金繰り悪化などで工事続行が困難になったりする場合に備え、契約解除や変更に関する条件を明確にします。具体的には、発注者や受注者の責任による解除と、天災など不可抗力による解除の取り扱いを区分して記載するのが一般的です。工期延長が発生した場合の再協議方法なども盛り込むとよいでしょう。
6. 保証・アフターメンテナンス
工事完了後に不具合が発見された場合の補修・保証に関する取り決めを記載します。住宅や建物の建築工事であれば、住宅瑕疵担保責任保険や建築士法などの法律に基づく保証の適用範囲と期間、申請方法などを詳しく示す必要があります。
7. 紛争処理・管轄裁判所
契約の履行中に紛争が生じた場合に、どのように解決を図るかを記載します。仲裁機関や調停、訴訟を行う場合の管轄裁判所(通常は工事場所または受注者の所在地の裁判所が多い)を明記することが多いです。これによって裁判管轄を巡る混乱を避けることができます。
作成時の注意点
工事請負契約書を作成するうえで、注意すべきポイントはいくつかあります。トラブルや法的リスクを回避するためにも、以下の点を意識しておきましょう。
明確な言葉遣いと数値の記載
工事の仕様や期間、金額の記載が曖昧だと、後から「言った・言わない」のトラブルに発展します。例えば、「おおむね○○までに完了する」などの表現は避け、具体的な年月日や数量を示すことが重要です。また、図面や仕様書など別添資料がある場合は、契約書の中でそれらを添付書類として明示し、相互に参照できるようにします。
記名・押印(電子契約の場合は電子署名)
日本国内では従来、契約書には記名・押印が行われるケースが主流ですが、電子契約の普及にともない、電子署名を用いた契約締結も増えています。電子契約の場合は、契約書の改ざん防止やタイムスタンプの付与などを行い、法的効力を明確に確保することが求められます。
建設業法や関係法令の遵守
建設業を営む場合、建設業法をはじめとする関連法令の定めがあります。一定金額以上の工事を請け負う場合には、建設業許可の有無や業種区分などが問題になるため、契約書には建設業許可番号や許可年月日などを明示する必要がある場合があります。
また、「建築一式工事」はもちろん、内装仕上工事業や電気工事業など、許可を受けている業種に合致しているかを確認しておきましょう。契約内容が許可範囲外の工事に及ぶと、違法となるリスクがあります。
請負契約印紙代の実務上のポイント
工事請負契約書には、印紙税法に基づく印紙の貼り付けが必要となる場合があります。印紙税は契約書の種類や記載金額に応じて税額が異なるため、間違えないよう注意が必要です。
1. 記載金額による税額の違い
請負契約書の記載金額が1万円以上の場合、基本的に印紙税が発生します。例えば、記載金額が500万円超1,000万円以下の場合には1万円の印紙税が必要など、累進的に設定されています。金額の区分と印紙税額は定期的に改正されることがあるため、最新情報を国税庁のサイトなどで確認することが大切です。
2. 収入印紙の貼り付けと消印
工事請負契約書を紙で作成する場合は、所定金額の収入印紙を貼り付け、消印(割印)する必要があります。契約書を2部作成する場合、それぞれに印紙が必要かどうかは契約の性質や当事者の扱い方によって変わります。一般的には、発注者・受注者がそれぞれ1通ずつ保管するので、両方の書類に印紙を貼るケースが多いです。しかし実務上は、どちらか一方が印紙を貼り付けて税額を負担し、もう一方の書類には貼らない扱いも見受けられます。
この場合でも、貼っていない書類は法的効力に影響はありませんが、税務上の問題が発生しないよう、どちらの書類に印紙を貼るか当事者間でしっかり合意しておきましょう。
3. 電子契約の場合の印紙税
昨今増えている電子契約の場合、契約書を紙で作成しないため印紙税が課税されないのが一般的です。ただし、電子データでも印紙税が課税されることがあるのでは?と疑問を持つ方もいますが、現時点では国税庁の見解によると、電子契約書に印紙税は課されないとされています。その分、適切な電子署名やタイムスタンプの付与で、法的に有効な契約書であることを証明できるようにしておくことが必須です。
工事請負契約書の重要性とトラブル防止
工事請負契約書は、**「いつ、どこで、誰が、どのような工事をどの条件で行うか」**をはっきりと示す、いわば工事の設計図のような存在です。万一、工事が期待どおりに進まなかったり、追加工事が発生したり、支払いが滞ったりといったトラブルが起きた際、契約書に明記されている内容が根拠として機能します。
トラブルを防ぐためのポイント
- 契約書のドラフト段階で発注者と十分に協議する
曖昧な表現や不十分な取り決めが残らないよう、ドラフトの段階でしっかり協議を重ねましょう。 - 契約書と図面・仕様書との整合性を確認
記載事項に食い違いがあると、後から「契約書通りではない」という異議が出る場合があります。 - 追加工事や変更工事の扱いを明確化
工事途中での仕様変更は珍しくありません。変更手続きや費用負担のルールをきちんと定めることが大切です。 - 法令遵守と建設業許可範囲の確認
法令違反に問われると工事全体がストップしてしまうリスクがあります。許可範囲や法令を把握し、必要があれば専門家の力を借りましょう。 - 印紙税の処理や電子契約の適切な導入
印紙の貼り忘れや消印漏れは、後々追加徴収される可能性があります。電子契約を導入する場合は、セキュリティや署名の正当性をチェックしましょう。
まとめ
工事請負契約書は、建設業界だけでなく、設備工事や内装工事などさまざまな分野において、工事に関する基本的なルールを明文化する重要書類です。
- 工事請負契約書と建築請負契約書は基本的には同じ目的で用いられるが、工事の範囲によって呼び分ける場合がある
- 工事請負契約書の基本構成には、当事者情報、工事内容、工期、契約金額、解除・変更条件、保証・アフターフォローなどが含まれる
- 作成時には建設業法など関連法令を遵守し、記載内容や支払い条件を明確にすることでトラブルを防止
- 請負契約印紙代は工事金額に応じて必要になる。電子契約であれば印紙税は不要だが、電子署名などを適切に行う必要がある
工事請負契約書をしっかりと作成しておけば、工事途中での変更や不測の事態が生じても、冷静かつスムーズに対処できる確率が高まります。ひいては発注者との信頼関係を強固にし、業務効率や品質向上にもつながるでしょう。ぜひ本記事の内容を参考に、より安全でスムーズな工事契約の締結を目指してください。
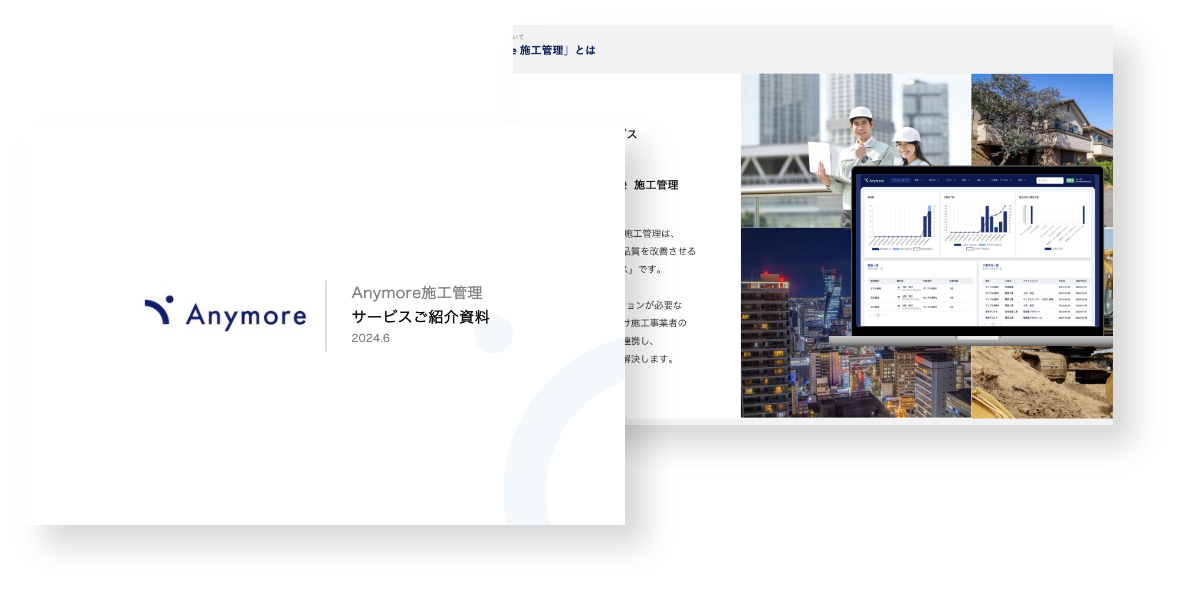
サービス資料ダウンロード
工程表の作成や複数案件横断での工程管理を効率化したい担当者様向けに、劇的な業務効率化につながる施工管理アプリ「Anymore施工管理」の概要について紹介しています。


