
【建設業】工程表とは?実施工程表など5種類の工程表を比較。
公開日:2025.01.17
▼ 目次
建設工事で欠かせない「工程表」とは?本記事では、バーチャートやガントチャート、グラフ式、工程管理曲線、ネットワークといった代表的な5種類の工程表を紹介・比較し、それぞれの意味や使い方を解説します。スケジュール管理や工事進捗率、出来高管理に役立つ工程表を活用して、より効率的な施工管理を目指しましょう。
関連記事:【建設業】カレンダー式工程表の無料エクセルテンプレート3選!
関連記事:【工程表】ガントチャート式工程表とは?使い分けや特徴について解説。
1. 工程表(行程表)とは?
「工程表」は、建設工事や製造、各種プロジェクトにおいて、全体的なスケジュールや進捗を可視化する「管理表」のことです。いつ、どの作業を行い、どれだけの出来高を積み上げていくかを表すことで、担当者間の情報共有を円滑にし、工事進捗率を的確に把握できます。工程表は「行程表」や「日程表」、「予定表」と呼ばれることもあり、Excelで作成したり、専用ソフトを活用したり、紙面上に図示するなど、さまざまな方法で運用可能です。
工程表を使うメリットは、計画的な工期管理やリスク対策、コミュニケーション活性化などが挙げられます。特に建築・土木などの分野では、複数の作業工程や協力業者が同時進行するため、誰がいつ、どの区画で何をするのかを明確化することで、手戻りやムダを減らし、コスト削減にもつながります。
2. 5種類の工程表比較
ここからは、建設業でよく用いられる5種類の工程表を紹介します。それぞれに特徴や得意分野があり、プロジェクトの性質や規模、管理者の好みに合わせて使い分けることが重要です。
【今回解説する5種類】
- バーチャート式工程表
- ガントチャート式工程表
- グラフ式工程表
- 工程管理曲線(累計曲線・Sカーブ)
- ネットワーク工程表(PERT/CPMなど)
以下、それぞれの意味や使い方、特長的な点を見ていきましょう。
3. バーチャート(Bar Chart)式工程表
バーチャートは、工程を棒状の長さで表す「棒グラフ型」の工程表です。縦軸に工程項目、横軸に時間をとり、各工程に対応するバーを引くことで、どの作業がいつ開始され、いつ終了するかを直感的に示すことができます。
特徴・メリット:
- 視覚的に分かりやすく、直線的な表示で全体像を俯瞰しやすい。
- 簡易な計画段階や小規模な工事に向いている。
- Excelなどで手軽に作成でき、工程変更への対応も容易。
留意点:
- 工程間の依存関係やクリティカルパスが明示されず、複雑なプロジェクトでは不足を感じる場合がある。
4. ガントチャート(Gantt Chart)式工程表
ガントチャートは、バーチャートの一種ですが、より詳細でプロジェクト管理ツールとして定番の工程表です。工程ごとの開始日・終了日・期間をバーで表す点はバーチャートに似ていますが、タスクの階層化、担当者割り当て、進捗度合いの記入など、機能面での拡張が可能です。
特徴・メリット:
- 多くのプロジェクト管理ソフトがガントチャート表示を標準搭載。
- 階層構造で大工程から小工程までブレークダウンしやすい。
- 進捗率をバー上で示すことができ、実施工程表として役立つ。
留意点:
- 複雑な相互依存を表現する際には、リンク機能や補助的な表現が必要。
- 縦軸が長くなりすぎると全体像が把握しにくい場合がある。
5. グラフ式工程表
グラフ式工程表は、工程をグラフ(折れ線グラフや曲線)で表現したもので、時間経過とともに出来高や進捗率がどのように累積されていくかを示します。例えば、工事進捗率の変化を折れ線グラフで描くことで、計画通りに進んでいるかどうかを直感的に把握できます。
特徴・メリット:
- 出来高管理や進捗率の把握に有効。
- 時系列での進捗傾向を一目で確認でき、遅れや前倒しの傾向を早期に察知可能。
- 計画曲線との比較で、実績とのギャップを明確化できる。
留意点:
- 工程間の論理的関係は表れにくい。
- 縦軸(出来高、進捗率など)やスケール設定に注意が必要。
6. 工程管理曲線(累計曲線・Sカーブ)
工程管理曲線は、累積出来高を時間軸上に積み上げた「Sカーブ」や「バナナ曲線」などで表現する手法です。特に「Sカーブ」と呼ばれる累計曲線は、初期は進捗が緩やかで、中盤にかけて急速に進み、終盤に再び緩やかになる、典型的なプロジェクトの進捗パターンを視覚化します。
特徴・メリット:
- 計画カーブと実績カーブを重ねて表示することで、遅れ・早まりを明確化。
- 一目で全体進捗を把握でき、累計出来高と目標値を比較することで、計画修正が容易。
留意点:
- 工程個別の詳細管理には不向きで、全体像の把握向き。
- どのように出来高を数値化し、累積するか、計算方法や基準づくりが重要。
7. ネットワーク工程表(PERT/CPM)
ネットワーク工程表は、作業間の依存関係をノード(作業)と矢印(関係)で表した図式で、PERT(Program Evaluation and Review Technique)やCPM(Critical Path Method)が代表的な手法です。各工程の先行・後続関係を明確にし、クリティカルパス(全体工期を決定する最も時間のかかる経路)を特定することができます。
特徴・メリット:
- 複雑な相互依存関係を明確化でき、工期短縮策を検討しやすい。
- クリティカルパスが明確となるため、どの工程が遅れると全体に影響するかが把握可能。
- 大規模で複雑な建築・土木工事、工場建設などで多用。
留意点:
- 作成・更新がやや複雑で、専門的知識が必要。
- 初期導入のハードルが高く、小規模プロジェクトには過剰な場合がある。
8. 選び方と活用方法
プロジェクトの性格や規模、管理者の目的によって最適な工程表は異なります。
- 小~中規模工事、単純な工程管理:バーチャートやガントチャート
- 進捗率や出来高を重視した計画・実績比較:グラフ式工程表、工程管理曲線(Sカーブ)
- 大規模・複雑な工事、クリティカルパス管理が必要:ネットワーク工程表(PERT/CPM)
また、これらを組み合わせて使うことも一般的です。例えば、ネットワーク工程表で全体構造を把握し、重要な作業を抽出したうえでガントチャートで進捗管理する、出来高は工程管理曲線でモニタリングするなど、多面的なアプローチが可能です。
Excelによる簡易作成や、専用の施工管理ソフト・プロジェクト管理ツールを用いることで、更新・編集も容易になります。工程表は「一度作ったら終わり」ではなく、進捗状況や変更点に合わせて随時見直し、改善していくことが大切です。
9. まとめ
工程表は、建設業などプロジェクト型のビジネスにおいて欠かせない「スケジュール管理」の要です。代表的な5種類を押さえておくことで、現場の状況や計画変更に柔軟に対応でき、より正確な工期予測や出来高管理が可能となります。
本記事のポイント:
- バーチャート/ガントチャート:視覚的で直感的な日程表。小~中規模に有効。
- グラフ式工程表/工程管理曲線(Sカーブ):出来高と進捗率の把握に適する。計画との差異分析に活用。
- ネットワーク工程表:複雑な依存関係の把握とクリティカルパスの特定に有効。大規模・複雑案件に向き。
プロジェクト特性に合わせた工程表を適切に選び、継続的な更新と分析を行うことで、より合理的な施工管理や進捗管理が可能になります。ぜひ、自社の事業規模や工法、チームのスキルに合わせて最適な工程表を導入してみてください。
おすすめツール:「Anymore施工管理」
「Anymore施工管理」は、工事進捗率管理やスケジュール管理を一元化できる施工管理ツールです。Anymore施工管理の工程管理機能では、ガントチャート式工程表を案件単位、案件横断で作成でき、担当者や担当会社によるフィルタにも対応しています。
また、LINE連携機能により、担当する工程の情報をLINEから確認・更新できるので、誰でも簡単に工程情報にアクセスすることができます。
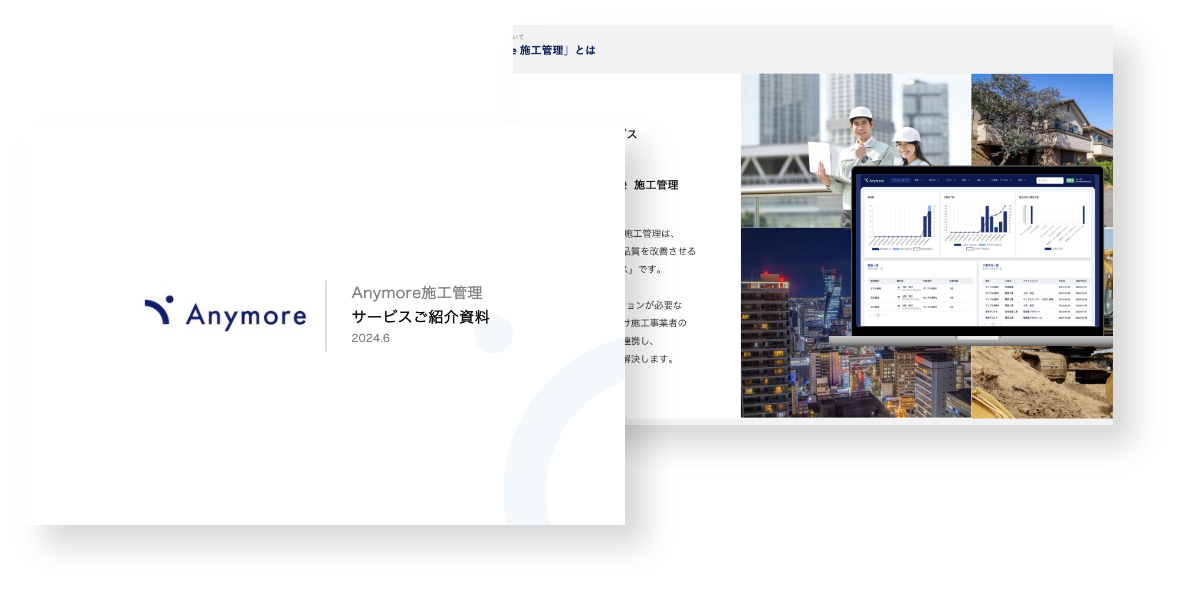
サービス資料ダウンロード
工程表の作成や複数案件横断での工程管理を効率化したい担当者様向けに、劇的な業務効率化につながる施工管理アプリ「Anymore施工管理」の概要について紹介しています。



